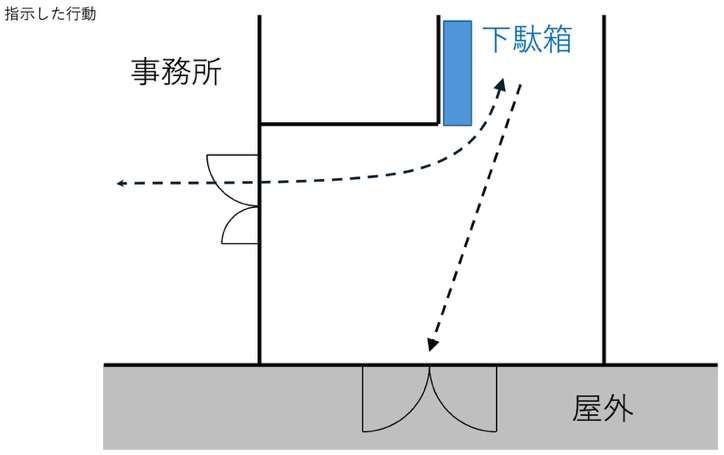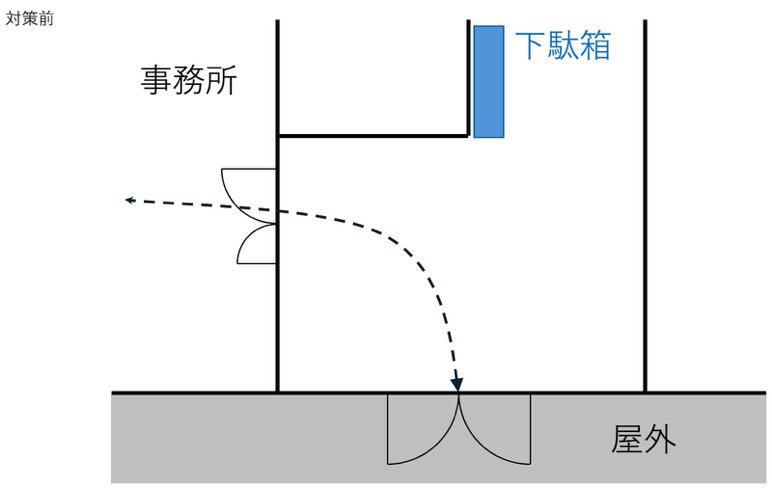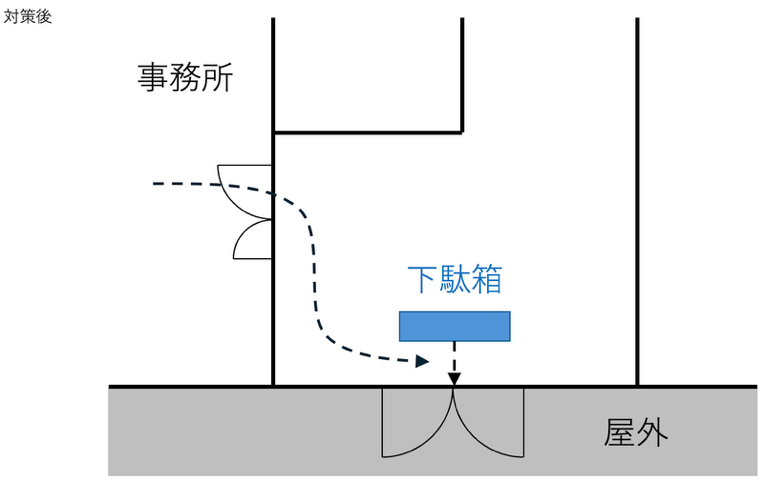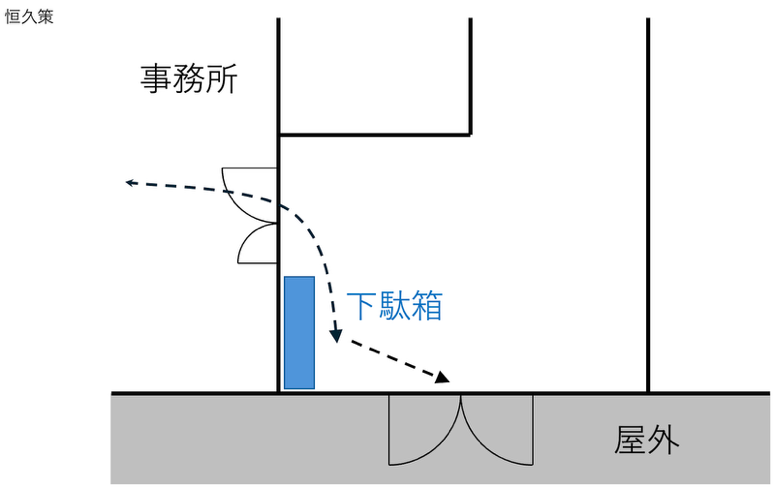素性の悪い考え方ややり方には、共通する「パターン」が存在します。このシリーズでは、そのパターンを取り上げ、本来最もムリなく合理的なアプローチを考えていきます。皆さんの身の回りや職場の「疲弊の原因」に当てはまるものはないか、そしてどうスマートに解決していくべきかの指針になれば幸いです。
◾️力に力で対抗するとは?
身近な例で言うと、車のアクセルとブレーキを同時に目一杯踏み込んでいる状態です。「誰もそんな非合理的なことはしないだろう」と思われるかもしれませんが、似たような構図は仕事や日常において頻繁に発生しています。
これらは全て、「発生した(あるいは発生する)負の力」に、「新たな別の力」をぶつけて相殺しようとする構図です。
例えば、皆さんの仕事や日常でこんな例はないでしょうか?
- ミスや手戻りが出る前提で、確認やチェック体制を過剰に強化する(ミスという力 vs チェックという力)
- 残業前提で、ギリギリの納期設定を行う(疲労という力 vs 根性という力)
- 汚れがひどいので、強力な洗剤で一気に掃除する(汚れという力 vs 洗剤という力)
- お酒を飲んでウコンを飲む(アルコール負荷という力 vs 肝機能サポートという力)
アクセルとブレーキを同時に踏むことがない人でも、上記の例に身に覚えのある方はいらっしゃるのではないでしょうか。この「力 vs 力」の構図こそが、私たちを疲弊させる「素性の悪いやり方」の代表格です。
◾️力に対抗していいのは圧倒的な力だけ
力に力で対抗することの最大の弱点は、その不安定さ、そして「拮抗状態は永続しない」という点にあります。人間が出す力のように、二つの力同士が拮抗している場合、どちらかが必ず消耗し、やがて抑え込めない(負けてしまう)瞬間が出てきます。最も分かりやすいのが、疲労です。
分かりやすい例として、重たい荷物を持ち上げることを考えてみてください。力自慢の人でも、長時間持ち続けようとすればプルプルと震え、不安定になります。これは、不安定で消耗戦だからです。
賢明な方であれば、荷物を高い位置に保ち続けるなら、圧倒的な力を持つ「机」に置くと思います。当然ながらその方が合理的です。これは、「力 対 力」ではなく「力 対 圧倒的な力」の構図であり、初めて安定がもたらされます。(壊れかけだったり、強度不足の机ではない前提ですが)
もう一つの例が、クサビです。クサビは、食い込むほどに応力(力)が大きくなるという特性を持ち、容易に「圧倒的な力」を生み出すことができます。事実、古くからある神社仏閣が、地震や台風が多い日本で長持ちできる理由の一つは、釘ではなくクサビ(や継手)で組まれているからです。これは、自然の力に対抗するために、常に力を出し続けるのではなく、構造的に圧倒的な安定性(圧倒的な力)を生み出す仕組みを採用している好例と言えます。
◾️最も素性がいいのは、元となる力を発生させない方法
いかにして「圧倒的な力」を用意するか、あるいは力を出し続けるかに知恵を絞るのも一策ですが、最も素性がよく、ムリや消耗が生じないのは、「そもそも元凶となる力」が発生しないようにすることです。
これは、言われれば「当たり前」の『根本解決』ですが、日常の中では「無理だ」と無視されたり、諦められたりしがちです。
先の例で言えば、「力 対 力」の構図を、「力を消す」に切り替えます。
- 汚れるから掃除する → そもそも汚れない仕組みを作る、あるいは汚れても良い場所・前提に変えてしまう。
- ミスが起こるからチェックを過剰にする → ミスが起こりにくいプロセスに組み替える。
- お酒を飲んでウコンを飲む → そもそもお酒を飲まない、もしくは酔っても問題がないような調整をする。
「それができれば苦労しない」と思われるかもしれませんが、冷静に、そして俯瞰的に考えれば、全く不可能ではないことが、日々の業務や生活の中に溢れています。「力 対 力」の消耗戦に慣れる前に、立ち止まって考えるべきなのです。
◾️一番の敵は慣れや怠慢
なぜ、冷静に考えれば可能な「根本解決」を避けてしまうのか?
それはひとえに、「力 対 力」の不安定で消耗する状態に慣れてしまっているか、あるいは変えることへの惰性(初期の面倒くささ)が勝ってしまうからです。ダイエットをしようと決意しても、目の前の誘惑に負けて計画を先送りするのと構造は同じです。
第三者から見れば、「最初の小さな苦労」を厭わなければ、その後の「大きな労力」が永続的に削減でき、トータルでは圧倒的に効率的な状態になれるのに、そうしない。これこそが、「素性の悪い考え方」に陥ってしまう原因です。
この「惰性の力」に素性良く対抗するために、我々が取るべき最も賢明な対策は、「常に変化し続けること」です。
「変化を拒む惰性の力」を下げるために、日頃から身軽な状態を保ち、「何かしらを変更し続けること自体が普通」という状態を維持する。そうすることで、消耗戦から抜け出し、よりスマートで創造的な活動に力を注ぐ。
それが「あるべき姿」です。